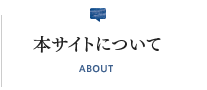数値の見方

「毎年、健康診断は受けているけど、結果の見方がよくわからない」そんなことはありませんか?主な検査項目の数値の見方や検査からわかることを知って、健康管理に役立てましょう。
肥満
BMIが比較的小さくても糖尿病などにかかりやすいことがわかっているので、油断大敵です。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| 肥満度 | 身長と体重から計算 身長(m)×身長(m)×22=適性体重 |
生活習慣病を引き起こす原因となる肥満を判断。肥満の度合は以下の数式で判定。 体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))=BMI値。一般的にはBMI値が25を超えると危険信号。 |
脂質代謝
脂質がどんどん血管の内側にたまって、動脈硬化になっても、まだ自覚症状がありません。心筋梗塞や脳梗塞になる前に日頃の管理が必要になります。また、女性は更年期になると、エストロゲンという女性ホルモンが減少するため、コレステロール値が高くなりやすいです。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| 総コレステロール(コレステロールCHOL) | 140~199mg/dl | 血液中に含まれるすべてのコレステロールを測定した総量を「総コレステロール」といいます。 コレステロールは、細胞膜の構成成分で重要な役割働き。 血液中のコレステロールが増えると、動脈硬化をはじめとするさまざまな病気を見つける手がかりになります。 |
| 中性脂肪(TG) | 150mg/dL未満 | 皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられている体内の脂肪の主成分の量を測定。 ※中性脂肪が多いと高脂血症から動脈硬化へと進み、脳卒中や心筋梗塞などの病気が発症する危険性が高まる。 |
| LDL(悪玉)コレステロール | 140mg/dL未満 (ただし120~139は境界域として治療対象) |
肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ働き。 LDLが増えると血管壁に溜まってしまい、動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を誘発するLDLの量を測定。 |
| HDL(善玉)コレステロール | 40mg/dL以上 | 細胞が使いきれなかったコレステロールを回収して、肝臓に戻す働き。血管内に付着する脂肪分を取り除き、動脈効果を防ぐHDLの量を測定。 HDLが少なすぎると動脈の壁に付着しているコレステロールを回収しきれず、動脈硬化を起こしやすくなる。 |
血圧
高血圧は日本人に多い病気です。自覚症状はほとんどないので、定期的に血圧を測っていないと、高血圧を発見することは難しいです。
高血圧をほっておくと、血管や心臓に障害をもたらすので、定期的にチェックする必要があります。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| 血圧 | 収縮時(最高)血圧130mmHg未満 拡張期(最低)血圧85 mmHg未満 |
脳卒中や心筋梗塞などの原因となる高血圧や低血圧などを判定。 ※血圧は時間帯や精神状態、運動などの状況により変化するため、日を変えて数回測定した平均値をみることが必要。 |
肝機能
「肝心要」とも言われるくらい極めて大切な肝臓。そのため、検査項目も多くなります。
肝臓は、24時間働き続けますが、ダメージを受けても症状に出にくいので、定期的な状態確認がお勧めです。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| GOT(AST) | 10~35 U/L | 肝臓に多く含まれるアミノ酸を作る酵素。肝細胞が破壊されると血液中に漏れ、数値は高くなる。肝炎や脂肪肝、肝臓がんなど、主に肝臓病を発見する手ががりとなる。 GOTとGPTの比率は肝障害の種類、進行によって変わるので、病気の具合をはかる目安になります。 |
| GPT(ALT) | 5~30 U/L | 肝臓に多く含まれるアミノ酸を作る酵素。肝細胞が破壊されると血液中に漏れ、数値は高くなる。肝炎や脂肪肝、肝臓がんなど、主に肝臓病を発見する手ががりとなる。 GOTとGPTの比率は肝障害の種類、進行によって変わるので、病気の具合をはかる目安になります。 |
| γ-GTP | 男性10~50 U/L 女性10~30 U/L |
アルコール性肝障害を調べる指標。 ※他の肝機能検査に異常がなくγ-GTPの数値だけが高いときは、アルコールの飲みすぎが考えられる。薬を長期間服用している場合にも上昇することがある。 |
| ALP | 100~350 U/L | 多くの臓器に含まれている酵素で、臓器に障害があると血液中に流れ出、主に胆道の病気を調べる指標となる。 |
| 総たんぱく(TP) | 6.5~8.0 g/dL | 血清中のたんぱく質の総量。高い場合は、慢性肝炎や肝硬変など、低い場合は、栄養不良や重い肝臓病が疑われる。 |
| 総ビリルビン(T.Bill) | 0.2~1.2 mg/dL | ヘモグロビンから作られる色素で、胆汁の成分。黄疸はビリルビン色素が増加した状態。 |
| ZTT(硫酸亜鉛試験) | 4~12 KU | 血液の濁りぐあいを測定。濁りが強いと数値は高くなり、慢性肝炎や肝硬変が疑われる。 |
糖代謝系
糖尿病は進行すると治りにくい病気です。また合併症を起こす糖尿病にならないためにも早期発見・生活習慣の改善で予防することが大切です。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| 空腹時血糖値(FBS・FBG) | 80~110未満 mg/dL | 糖尿病をチェックするための空腹時の血液中のブドウ糖の数値(血糖値)。 ※空腹時血糖が110~125mg/dLの場合は糖尿病の疑いが強いと診断され、ブドウ糖負荷試験を行ってさらに詳しく調べる。 |
| 尿酸(UA) | 男性3.5~7.0 mg/dL 女性2.5~6.0 mg/dL |
細胞の核の成分・プリン体が分解してできる老廃物の量。代謝異常により濃度が高くなると、一部が結晶化し、それが関節にたまると痛風になる。 |
| HbA1C | 5.6%未満(JDS) 6.0%未満(NGSP) |
HbA1Cは120日以上血液中にあるため、長時間にわたる血糖の状態を調べることが可能。糖尿病の確定診断などの指標。 ※従来は日本独自の「JDS」による数値を利用、2012年4月からは、国際標準の「NGSP」による数値に変更。 |
| 尿糖 | (-) | 尿中の糖の有無。糖尿病を見つける指標のひとつ。陽性の場合は、糖尿病や膵炎、甲状腺の機能障害などの疑いがある。 |
血液
女性多い鉄欠乏症貧血。30代女性の5人に1人が貧血といなっています。酸素を臓器に運ぶ働きがあるため不足すると臓器の働きが低下します。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| 赤血球数(RBC) | 男性4.0~5.5 106/µL 女性3.5~5.0106/µL |
血液中の赤血球数。数値が低いと貧血や造血機能の低下、高値では多血症などが疑われます。 |
| ヘモグロビン(Hb) | 男性14.0~18.0 g/dL 女性12.0~16.0g/dL |
赤血球中の酸素を運ぶたんぱく質の一種。低値だと貧血が疑われる。 |
| ヘマトクリット(Ht) | 男性40.0~50.0% 女性35.0~45.0% |
血液中の赤血球の容積の割合(%)。低い場合は貧血の疑いがある。 |
| 白血球数(WBC) | 3.5~9.0 103/µL | 白血球は、外部から進入した病原体を攻撃する細胞の量。数値が高いと感染症や白血病、がんなどが疑われる。外傷や喫煙、ストレス、風邪などでも上昇。 |
尿・腎臓
腎臓が悪くなると、排泄物が変化して検査をすると早めに対処ができます。急性腎炎は比較的早く治りますが、慢性腎炎は治りにくい病気なので、早期発見、早期治療が大切です。
| 検査項目 | 基準値 | 検査からわかること |
|---|---|---|
| 尿たんぱく | (-) | 尿中のたんぱくの有無。激しい運動の後、過労状態のとき、発熱時などに高くなることもある。 |
| 尿潜血 | (-) | 尿中の血液の有無。陽性の場合、腎臓病や尿路系の炎症が疑われる。 |
| クレアチニン(Cr) | 男性0.5~1.0mg/dL 女0.4~0.8mg/dL |
腎臓の排泄能力をチェック。数値が高い場合、腎機能障害や腎不全が疑われる。 |
献血での検査成績表でも確認できる項目があります。
年1回の健康診断以外にも、ご自分で確認できる方法はあるので、日頃から健康を気にかけることが大切です。